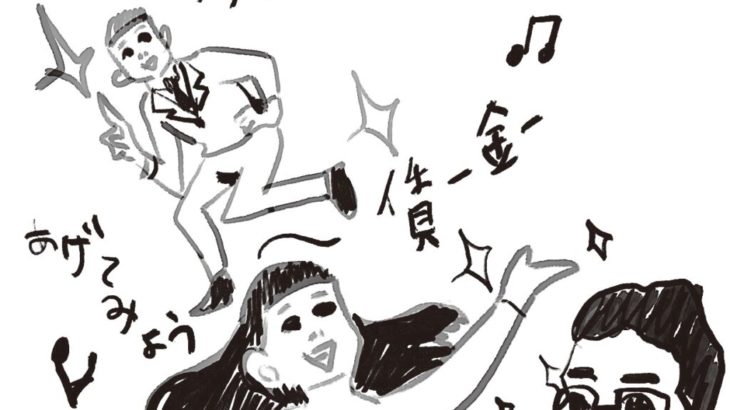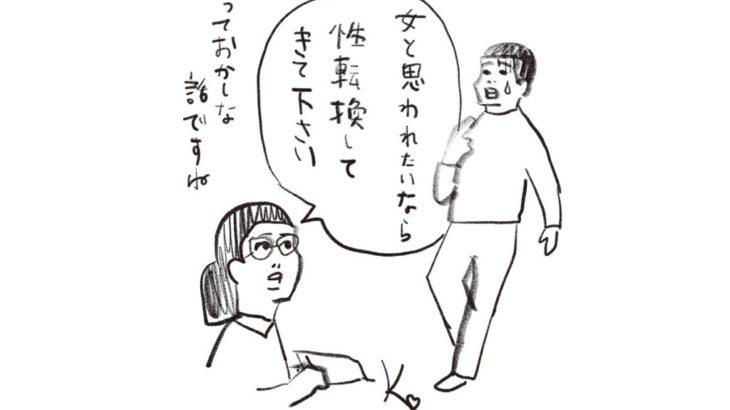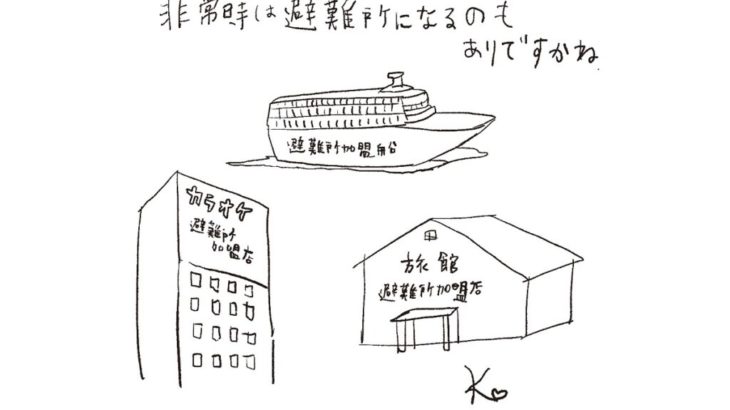日本のイラストレーションを牽引してきた立役者、宇野亞喜良さん。グラフィックデザイン、舞台美術、絵本、俳句など活動は多岐にわたり、現在、過去最大規模の「宇野亞喜良展」が開催中。今年90歳になったレジェンドにお話を聞いた。 ――『anan』は宇野亞喜良さんに長年お世話になっており、1970年、創刊間もない頃は「美術」としてファッションページにも関わっていらしたんですね。 (’70年11月発行の17号を見ながら)懐かしいですね。フェリーニの映画が好きだったので、“不思議の国のアリス”というテーマで人工美を追求するようなイメージで作りましたね。ダンサーや自称「女優」の男性や演劇実験室天井棧敷の役者などにモデルになってもらいました。 ――創刊第2号では宇野さんのアトリエにてファッション撮影。ご自身も登場なさっています。 そんなこともありました。写真の中の、壁にかけてあるのは横尾忠則の作品です。’60年代に買ったのだけれど、彼はこの絵が気に入って展覧会にしょっちゅう出すものだから、ほとんど僕の家にはなかったんです(笑)。 ――横尾忠則さんとは’60年代に一緒にイラストレーターの事務所を作られた仲。和田誠さんとも交流があったそうですね。 横尾君と僕はその前に日本デザインセンターというデザイン会社にいました。当時のボスは東京オリンピックのポスターをデザインした亀倉雄策さん。和田君は広告制作会社のライトパブリシティに勤めていて、勤務先がみんな銀座だったから、昼にはよく一緒に食事をしたりお茶を飲んだりしていましたね。 ――その後、3人でアニメーション映画も作られました。そうそうたるメンバーですね。 デザインセンターを辞める話を横尾君としていた頃、銀座に「みゆき族」というのが出始めていたんです。喫茶店で話をしていると、セーラー服の女の子が紙のバッグ(紙袋)を持って店に入ってくる。そしてトイレに入って出てきたら違う衣装になっているんです。長いスカートの裾にフリルがついていたり、装飾的でした。ヒールは履いていなかったな。お母さんに作ってもらったのか、知り合いの洋裁店に頼んだのか、オリジナルの服装ですごくかわいかった。銀座という街に適したファッションをして遊んで、制服に着替えて帰る。場に合わせて日常とは違う姿に変容する様が面白いなと思って見ていました。そんな時代です。 エロティック、背徳的なものに惹かれた。 ――宇野さんは名古屋のご出身。小さな頃から絵を描き、お母様が経営していた喫茶店に作品がたくさん飾られていた。16歳のときに新聞に取材されたのだとか。 坊主頭に学生服を着ている写真が新聞に載りました。父親が今でいうインテリアデザイナーをしていて、それを手伝っているうちにビジュアル系の仕事に興味が湧くようになったんです。お店の装飾をするときに、辞書で調べながら、看板の文字を僕が描いたり。名古屋って、喫茶店で時間を過ごす人が多いんですよね。 ――喫茶店文化の街と聞きます。 当時、母の店は小説新潮や文藝春秋、週刊誌や新聞各紙を揃えていて、お客さんはそれらを読みながらコーヒーを飲むんです。僕も子供の頃から、週刊誌に載っていた舟橋聖一の好色な小説を読んだりしていました。 ――「子供は読んではダメ」と言われなかったのですか? 僕のウチはそういうことは全く言われませんでしたね。 ――絵を描き始めたのはいくつくらいだったのでしょう? どこを描き始めというのかわからないけれど、名古屋が空襲にあうというので、小学2年生~6年生に疎開をしていたんですね。疎開先から家に葉書を出すのに、文章を書くのが苦手で、その日に食べたさつまいもなんかの絵を描いて送ってました。僕はサウスポーなので、小学生の頃は「左団子郎」なんてあだ名をつけられていました(笑)。顔が丸かったんです。 ――宇野さんの絵は細部に不思議な要素が加えられていて、様々な物語を想像させられます。そしてエロティックな魅力があります。 エロティックなものは好きですね。子供の頃から、雑誌の連載小説の裸の挿絵や、週刊誌のヌード写真を目にしていました。中学から高校まで大人に交じって「クロッキーの会」に通っていたんです。会費を払って、女性をモデルにデッサンをするのですが、ベレー帽をかぶったおじさんがいて、さぞかし上手だろうとスケッチブックをのぞいてみたらすごく下手だった。つまり、絵描きのふりをして、ストリップよりも安い料金で女性の裸を見に来ていたんです(笑)。 ――オマセな少年だったんですね。 ませていたのでしょうかね。中学の同級生に不良が一人いて、娼婦の家に泊まって、そこから登校していました。カッコいいなあと憧れました。背徳的なニュアンスがあるものが好きですね。 ――勉強はお好きでしたか? いや、ダメだったと思いますよ。疎開先からの葉書も絵で誤魔化すくらいですから。母の店にはいろんな雑誌が置いてあったので、いわゆる絵画よりも挿絵に惹かれていましたね。あらゆる挿絵をたくさん模写していました。雑誌名と何年何月号の何ページまで書き写して、自分なりのビジュアル辞書のようなものを作ったんです。「絵の辞書」と書くのもカッコ悪いから、和英辞典で調べて初めて「イラストレーション」という言葉に出合い、「Dictionary of Illustration」と英語で書きました。 ――当時からグラフィックデザインやレイアウトに意識が向いていたのですね? そういうところもあったのかもしれません。『少年』と『少年倶楽部』という雑誌をとっていて、妹は『少女』と『少女倶楽部』をとっていたんです。僕はその両方を読んでいました。そのうち妹は中原淳一さんの『それいゆ』を読み始めた。中原さんや内藤ルネさん、長沢節さんらの絵を見ていました。デザイナーになって上京してから、そういう方々にお会いできたのは嬉しかったですね。幼少期から出版物にたくさん触れていたから、イラストレーションを描くようになったのでしょうね。 ――作品が印刷物になるときに原画に忠実であることを求める画家が多いのに対して、宇野さんは印刷物として魅力的であればいいというお考えだと伺いました。 もともと印刷物が好きというのもありますが、印刷技術によって、絵が変わって見えたり、変容していくことが僕のテーマの一つでもあると思います。 ――演劇のポスターや、舞台美術も多く手がけてこられましたが、演劇に興味を持つようになったきっかけは何だったのでしょう? 父親は昔、NHKの放送劇の劇団員だったことがあったらしいです。僕はその姿を見聞きしていないのですが、昔の写真を見ると、父が菊池寛全集を手にしていたり、本棚にはたくさんの戯曲がありました。子供の頃は、知り合いのつてで、御園座という劇場の照明室から歌舞伎を観せてもらったりしていたんです。劇団民藝が戦後最初にやった公演も観に行きましたし、疎開から名古屋に戻ってから上京する21歳まで、歌舞伎、松竹新喜劇、前進座などあらゆる種類の舞台を観ていましたね。 ――演じてみたいと思ったことはないのですか? 役者の側に回ろうと思ったことはないですね。芝居が好きで、若い頃、演劇をやっている先輩に頼まれて絵を描いたのだけれど、「君の絵はセンチメンタル。これからの日本を建設的に考えるときに、こういうセンチメンタリズムではダメだよ」と言われた。自分の思想で日本をどう組み立てていくかなど考えないで、スポンサー付きの、人の言いたいテーマを請け負ってやっていくデザイナーだったら文句はないだろうというふてくされた気持ちが芽生えました。 ――宇野さんは、’70年代の演劇や雑誌に社会的影響力があり、とても熱かった時代を第一線で体感されています。今や全てがスマートフォンの中で完結しているような時代。現在のカルチャーについてはどう思われますか? 社会を俯瞰する人にとっては当然いろんな思いがあるのでしょうが、その気になって情報を集めればきっとどのジャンルも面白い現象は生まれているのだと思います。ただ僕は不勉強で携帯も持っていないので(笑)。でも、先日『ゴジラ‐1.0』が米国アカデミー賞(視覚効果賞)を獲りましたよね? 日本の映画がアメリカで認められるようになるなんて思いませんでした。初代の『ゴジラ』は当時の同僚だったデザイナーの木村恒久と観ました。彼はすごく興奮していたけれど、僕はもっとゴジラを巨大に見せるアングルで撮ればいいのにと不満があった。新しいゴジラは進化しているそうなので、観に行きたいと思っています。 ――70年以上描き続けてこられて、絵に対して興味を失うことはなかったのでしょうか。 きっとあったのでしょうけどね。そういう気持ちをうまく誤魔化して通用しちゃったのでしょうね。演劇や映画が好きで、虚構を創ることが好きだったから、なんとかやっていきたいという一種の芸人根性のようなものもあったのかもしれません。木村恒久が僕のことを書いた文章があって、谷崎潤一郎の小説の『刺青』の清吉に似ていると。女を眠らせている間に刺青を彫る男です。最後に「宇野亞喜良は幇間(ほうかん)がいちばんピッタリだろう」と締められていた。いわゆる太鼓持ちです。媒体がお座敷。スポンサーを喜ばせ、女性たちも楽しませて、自分も結構それが気に入っている。うまい比喩だなあと思いましたね。 ――制約なしに自発的に絵を描かれることはあるのですか? それが案外ないんですよ。スポンサードされ、テーマを与えられて、それをどう表現するか考えるのが好きです。 ――描くことは今も楽しいですか。 アイデアがまとまるまでは時間がかかりますけど、楽しい地点まで辿り着くと面白いです。夢中になって日3枚描くこともあります。アナログなので、絵をいろんなサイズにコピーして、切り貼りしながら、こうして遊ぶみたいに一枚のポスターを作り上げています。 宇野さんのこれまでの膨大な仕事を振り返る「宇野亞喜良展 AQUIRAX UNO」が東京オペラシティ アートギャラリーにて6月16日まで開催中。学生時代のスケッチから、グラフィックデザイナーとしての仕事、アニメーション映画、ポスター、絵本、版画、装丁、立体作品やプロデュースした舞台関係の作品まで幅広く展示。美しく耽美な世界を堪能できる。TEL:050・5541・8600 うの・あきら 1934年生まれ、愛知県出身。’55年に上京。カルピス食品工業、日本デザインセンターなどを経てフリーに。’60年代には寺山修司主宰の演劇実験室天井棧敷などのアングラ演劇ポスターや舞台美術を担当。’90年代は舞台の美術監督を務めたり、「左亭」の俳号で俳句とのコラボレーション作品を発表。’60年日宣美展会員賞、2008年日本絵本賞、’15年読売演劇大賞選考委員特別賞ほか受賞多数。1999年に紫綬褒章、2010年に旭日小綬章を受章。 ※『anan』2024年5月1日号より。写真・玉村敬太 インタビュー、文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/546192/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。 今回のテーマは「日経平均株価」です。 株価上昇と暮らし、直結しているわけではない。 日経平均株価が史上最高値を更新、3月に初の4万円台に乗せたと大きく報道されました。しかし、日本の株価が値上がりしても、景気が良くなった実感を得られない人がほとんどです。 そもそも日経平均株価は、日本全体の企業の株価の平均値ではありません。「日経225」という、日本経済新聞社が東証プライム上場銘柄から選んだ、225の銘柄の平均株価です。幅広い業種から選定されていますが、グローバルに展開する大企業ばかりでベンチャー企業は入っていません。日本は9割以上が中小企業ですから、日経平均株価が上がっても、大企業が海外で儲けて、海外に投資しているという状況で、日本国内の雇用や賃金にダイレクトに反映されるものではないんですね。 今年の春闘では、平均5%超の賃上げ率となりました。しかし、物価上昇を考えると、23か月連続でマイナスとなっている実質賃金がプラスに転じるかはわかりません。にもかかわらず、日銀はマイナス金利の解除や金利の引き上げを決定したため、大変心配です。 企業がなかなか賃金を上げられなかった理由の一つは、給料を上げると社会保険料の負担も増えてしまうからです。売り上げが落ち、給料を支払えない状況に陥っても社会保険料の請求は続きますので、中小企業の経営者は簡単には賃上げすることができません。そんななか、大分県と群馬県は自治体が企業に奨励金や補助金を出し、物価上昇を上回る賃上げに成功しました。いま国がやるべき政策は、消費税の免除や、社会保険料をいったん凍結するなど、市民の負担感を減らし、豊かさを実感させることだと思います。 株価が上がるというのは、会社の財政の健全性や、その事業に対する将来性を見込まれたということです。ただ、いま日本企業の株が海外投資家に買われているのは、「安いから」という理由もあります。せっかく日本株が買われているのだから、大企業は国内に投資をして、雇用を生み、従業員の賃金が上がる流れを作ってほしいと、国も経済界もリクエストしています。足元のローカル企業を育成しなければ、日本の経済は復活しませんし、将来的な成長も見込めないでしょう。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年5月1日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/546227/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「ダブルケア」です。 晩婚や晩産により増大する問題。社会全体で解決を。 「ダブルケア」とは、育児と介護が同時期に発生している状態のことを指します。晩婚と出産年齢の高齢化により、この問題が指摘されるようになりました。内閣府は平成28年に27年度の「育児と介護のダブルケアの実態に関する調査」を公開。それによると当時のダブルケアの推計人口は全国に25.3万人。そのうち女性は16.8万人で男性は8.5万人でした。その後も晩婚化、晩産化は進んでおり、今年毎日新聞が国の統計から推計した数字では、ダブルケアに直面している人は29万3700人にのぼるとされています。 ダブルケア当事者は30代、40代が多く、働き盛りの世代。育児も介護も女性が担うことが多く、女性が仕事を辞めざるを得ないというのが深刻な問題としてあります。調査では、ダブルケアを行う無業の女性の約6割が就業を希望。働いて家計を助けたいけれども、約8割が、育児や介護を抱えながらでは非正規雇用でないと働けないと答えています。育児のみを行う無業の女性も同じ傾向なので、働き方の構造的な問題といえます。ダブルケアを行う男性の半数以上が、配偶者からほぼ毎日手助けを得ているのに対して、女性は4人に1人にとどまっています。女性が一人で抱え込んでしまっているケースが少なくないんですね。 ダブルケアに携わる女性が、充実させてほしいと希望している第1位は休暇・休業を取得しやすい職場環境の整備。続いて、上司や同僚の理解、テレワークやフレックスタイムの導入でした。企業は、ダブルケアに対応する就労システムの導入が今後の課題になります。当事者に聞くと「急な対応を迫られた時に、すぐに駆けつけて助けてくれる人がほしい」と話していました。提案ですが、育児や介護の人材派遣を公共事業として立ち上げてみてはどうでしょうか。消防や警察のように、育児や介護を手伝うレスキュー隊員的役割を公務員が担うのです。 ついに中国でも人口減少が始まり、東アジアでは超少子化、高齢化が進み、ダブルケアは東アジア全体の問題になりつつあります。この分野の課題解決に各国で相互交流、連帯をする必要があるのかもしれません。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年4月24日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/544156/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「脳埋め込みデバイス」です。 神経回路の損傷を補足するための脳インプラント。 脳とコンピューターをつなぐブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)を開発する会社「ニューラリンク」。1月末に初めて人間の脳にデバイスを埋め込む臨床試験を実施したと、創設者のイーロン・マスク氏が発表しました。被験者は、直接手を動かすことなく、思考するだけでコンピューターのカーソルを動かせるようになります。ワイヤレスでそれが可能になったというのは画期的なことでした。 脳に埋め込むとはいえ、ニューラリンクが接触するのは、体を動かす機能に関わる大脳の外側部分です。頸髄を損傷したり、筋萎縮性側索硬化症(ALS)などにより、四肢を自由に動かせない患者が、PCやロボットアームなどの機器を操作できるようになることを目的に開発しています。ですから、イマジネーションなど、いわゆる思考そのものに携わる脳の深層部に働きかけるわけではありません。 BMIの分野は、今世界で注目されています。日本でも大阪大学の平田雅之教授率いる研究室が、ワイヤレス体内埋込型BMI/ブレイン・コンピューター・インターフェイス(BCI)を研究しており、医療機器のベンチャーとして「JiMED(ジーメド)」を2020年に設立しました。ニューラリンクをはじめ、欧米のBMIは主に「侵襲型」といって、デバイスを直接脳に繋げて脳波を計測します。しかし、脳はデリケートな臓器ですから、直接埋め込むのは大変なリスクも伴います。日本では「低侵襲型」という、脳への負担を軽減した技術の開発を積極的に進めようとしています。低侵襲型は、侵襲型に比べて精度が低いといわれていましたが、最近の研究ではほぼ同等のデータを得ることが可能になりました。 脳科学者の茂木健一郎さんは、これを機に、自分の脳への興味を深めてほしいと話していました。今後、議論が必要になるのは倫理の領域でしょう。研究開発がさらに進み、脳の思考を司る部分までもが人工的にコントロール可能になった時に、誰が何の目的でそれを使うのか。デバイスがハッキングされることはないのか。あらゆるリスクを考え、事前に議論をし、対策をとっておかないと危険だと思います。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年4月10日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/541705/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「性同一性障害特例法」です。 まだ小さな一歩。あらゆる人の人権を守る法律を。 昨年10月、性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するために、生殖能力をなくす手術を受ける必要があるとする法律は、人権侵害にあたり憲法に違反すると最高裁判所が判断しました。 現在「性同一性障害特例法」では、戸籍上の性別変更を認める要件として、【1】18歳以上。【2】現在結婚していない。【3】未成年の子供がいない。【4】生殖腺や生殖機能がない。【5】変更後の性別に似た性器の外観を備えている。加えて、2人以上の医師から性同一性障害の診断を受ける必要があると定めています。【4】と【5】を満たすためには、事実上、手術を受けなければいけません。しかし、体に傷をつけないと、自分の性別が認められないと法律で定めているというのはとても理不尽な話です。 ちなみに、最高裁が法律の規定を憲法違反と判断したのは、戦後12例目。違憲判決を勝ち取るのはとてもハードルの高いことなんですね。この判決が下った背景には、セクシュアリティの問題に対して、保守的だったカトリック教国が理解を示しはじめたという世界的な潮流があります。ローマ教皇庁が同性カップルへの祝福やトランスジェンダーの洗礼を容認したことも大きく影響しているでしょう。 2012年、アルゼンチンで初めて精神科医の診断なしに性別変更を可能とする法律が制定され、続いてデンマークやマルタなども同様の法律を施行しました。’13年にはアメリカ精神医学会で「障害」という言葉を使わず、「性別違和」と呼ぶことに。’17年、欧州人権裁判所が性別変更のために生殖能力をなくす手術を課すことは人権侵害という判断を下し、’18年にWHOは国際疾病分類の改定で、生まれた時に割り当てられた性別と、自認する性別が異なる状態を「ジェンダー・インコングルエンス」として精神や行動などの障害から外し、「性の健康に関する状態」に分類しました。現在、医師の診断書なしに性別変更が認められる国は欧州を中心に11か国にのぼります。 日本では’22年までに全国の家庭裁判所で1万1919人の性別変更が認められました。性同一性障害特例法の要件は本当に必要なものなのか、議論を求める声が上がっています。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年4月3日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/540178/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「世界選挙イヤー」です。 本当の民主主義が危うい状況。政治不信の払拭は急務。 今年は世界50の国や地域で、国のトップを選ぶ、大選挙イヤーです。関わる有権者は約20億人に及ぶといわれています。すでにバングラデシュ、台湾、エルサルバドル、アゼルバイジャン、パキスタン、フィンランド、インドネシアでの選挙が終わり、これからロシア、韓国、インド、ウクライナ、欧州議会など、11月にはアメリカ大統領選挙もあります。 選挙という民主的な手続きは取られていますが、ロシアや北朝鮮のように権力者が続投し続ける「名ばかり民主主義」の国が実は増えています。インドもモディ首相が3期目を務めるだろうといわれています。アメリカ大統領選挙では、バイデン大統領とトランプ前大統領の一騎打ちが濃厚。しかし、トランプ氏は4つの刑事事件で起訴されています。「有罪でも大統領になれば、恩赦もしくは不起訴にできる」となると、法治国家の基盤が根底から覆されることになってしまいます。 1月に台湾総統選を取材しましたが、台湾では投票のために帰国する人が多く、成田も羽田も空港は台湾人で溢れていました。日本で働く29歳のある台湾人女性は、普段から政治に関心が強いわけではないけれど、国の未来を決める一票なので、投票するのは当たり前だと話していました。10代の頃にひまわり学生運動を友達と見に行き、皆で声をあげる大切さを知り、意識が変わったのだそうです。支持する党派にかかわらず、有権者たちは一様に「政治汚職を断ち切ってほしい」と訴えていました。政治への不信感が募ると、他国による認知戦により内側から崩されかねません。大きな選挙があるということは、その国の政治を変えやすい状況が生まれますから、「選挙介入」のリスクが高まります。台湾総統選も中国の介入をどう防ぐかがテーマになっていました。欧州では「暮らしが良くならないのはウクライナ支援をしているから」というような認知戦をロシアが仕掛け、「ウクライナを支援する政治家を選ぶな」というムードを作り、欧州議会選挙に揺さぶりをかけています。選挙制度を利用した権威主義が増えると、世界はより独裁的なパワーが強くなりますから、注意が必要です。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年3月13日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/536504/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「能登半島地震2 避難の課題」です。 1次産業従事者が多いからこそ、難しい県外避難。 能登半島地震は、発生から1か月経った2月5日現在、石川県内で約3万9000戸が断水、能登地方では約1800戸で停電が続いており、厳しい生活を強いられています。石川県内の避難所で生活をしている人は約1万4000人います。 生活を立て直すまで、ホテルや旅館などの2次避難先に移ることを県は推奨しています。しかし、県内と隣県の施設に5000人以上が移ったほかは、27都道府県に確保した2万人以上分の受け入れ先は利用されていません。 それは、被災した能登の多くの人が第1次産業の漁業や畜産業、伝統工芸など、土地に根付いた仕事に就いているため、土地を離れると生業そのものを失うからです。僕が取材に行った時にも、家も牛舎も傾いた危険な状況にもかかわらず、牛を置いていけないと語る被災者の方がいらっしゃいました。 地域をいつくらいまでに再生させるなど、将来の復興計画を示さなければ、土地を離れたら戻ってこられないのではないかと、遠くに避難することを躊躇してしまいます。若い世代も、自分たちの故郷が将来、失われてしまうのではという不安を抱えています。短期的な緊急支援とともに、長期的な町の復興支援を考えなければいけません。 もう一つ明らかになったのは、老老避難の問題です。高齢者がさらに高齢の住民を避難させ、避難所でサポートしなければいけない。輪島市のある地区では、76歳の区長が町内では若手として避難所の運営を任されていました。これまでの豪雨災害や土砂災害でも、高齢者から優先的に避難を促されましたが、実際には避難したくても動けないという問題が頻出していました。 能登では、心を病む、持病が悪化するなど、災害関連死の問題が深刻化しています。避難所の環境も良いとはいえません。学校の体育館を避難所にすることが多いですが、ダンボールを敷いたところで冷たい床で快適に過ごすのは至難の業です。これだけ災害の多い国ですから、既存の施設を避難所に転用するのではなく、避難のための施設をきちんと整備して、逆にそれを平時にどう利用するかという発想に転換する必要があるのではないでしょうか。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年2月28日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/534445/ Source: ananweb
意外と知らない社会的な問題について、ジャーナリストの堀潤さんが解説する「堀潤の社会のじかん」。今回のテーマは「能登半島地震」です。 通信手段を失い、幹線道路は1本。半島ゆえの難題。 元日に能登半島で起きた大地震。発生後1か月経っても、地震活動は活発で注意が必要な状態が続いています。 災害時には僕はLINE IDを公開し、「発信支援の必要な方は連絡を」と呼びかけています。地震発生直後に約230件が届きましたが、今回はどの情報が本当に支援を必要としている方からなのかを精査する必要がありました。情報が古かったり、厚意で転送してくださったXなどSNS上のヘルプ要請も真偽の判断がつかないものがありました。インプレッションを増やすために偽の住所を書いて助けを呼ぶ投稿が多数アップされていたからです。直接連絡の取れた方の情報をもとに現地入りしましたが、道路が分断され車が入れないところは徒歩で山を越えなければいけませんでした。 今回、支援の初動が遅れた理由の一つは、情報インフラが途絶えてしまったことです。山中では、電波の入る場所を必死に探す人たちに大勢会いました。震央に近い穴水町は、役所に災害対策本部を立てたものの、通信障害により県庁とのホットラインが使えなくなっていました。NHKですら中継基地局が電力不足で放送不可に。被害状況を伝えることも、災害の全体像を掴むこともできない状態でした。僕も知り合いの議員らに窮状を訴え、ある議員の働きかけで、スペースX社の衛星通信サービス「スターリンク」を能登に提供してもらえることになりました。 もう一つ、今回ネックになったのは、半島という地理的な理由です。東日本大震災も熊本地震や西日本豪雨も、大きな災害でしたが周辺自治体からすぐに支援に入ることができました。しかし能登半島の北端は金沢からも約140km、東京から静岡ほどの距離があります。幹線道路は1本しかなく途中で寸断されました。海岸線は地形が変化し、接岸できる場所が限られ、船で海から支援に入るのも難しい状況でした。 被災したのは、高齢者の多い過疎の僻地で古い家屋が多く、倒壊を免れませんでした。同じような問題を抱える地域は全国にたくさんあり、都市とは違う防災のあり方を考えなければなりません。能登半島地震は、地方が抱える問題を集約した災害といえます。 ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。 ※『anan』2024年2月21日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子 (by anan編集部) https://ananweb.jp/news/532773/ Source: ananweb